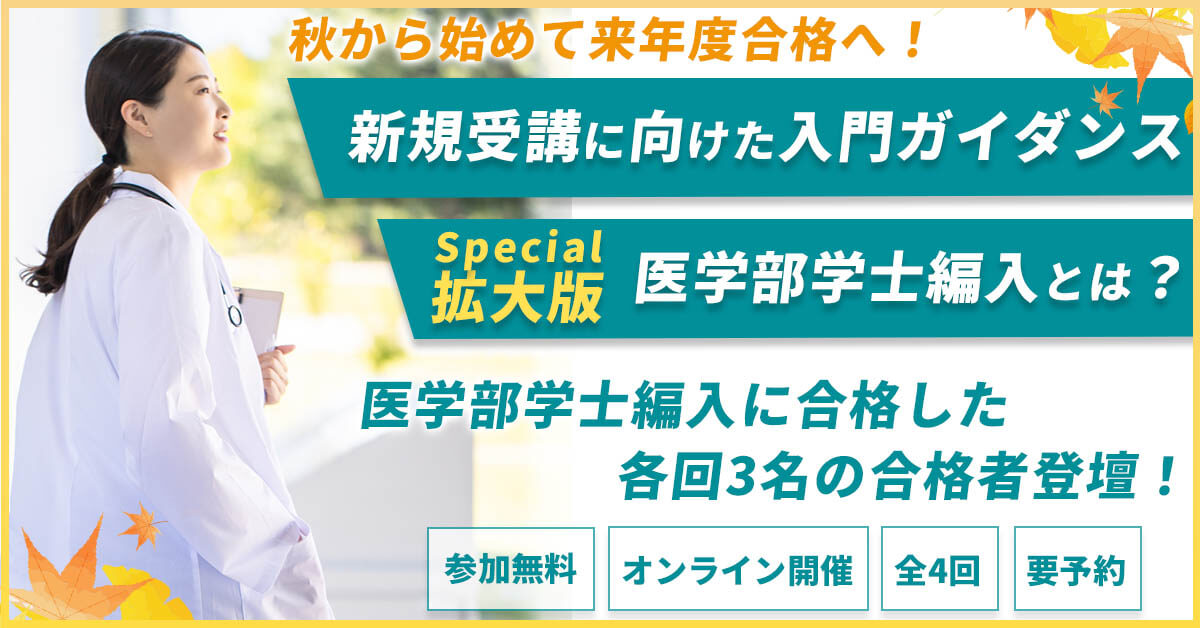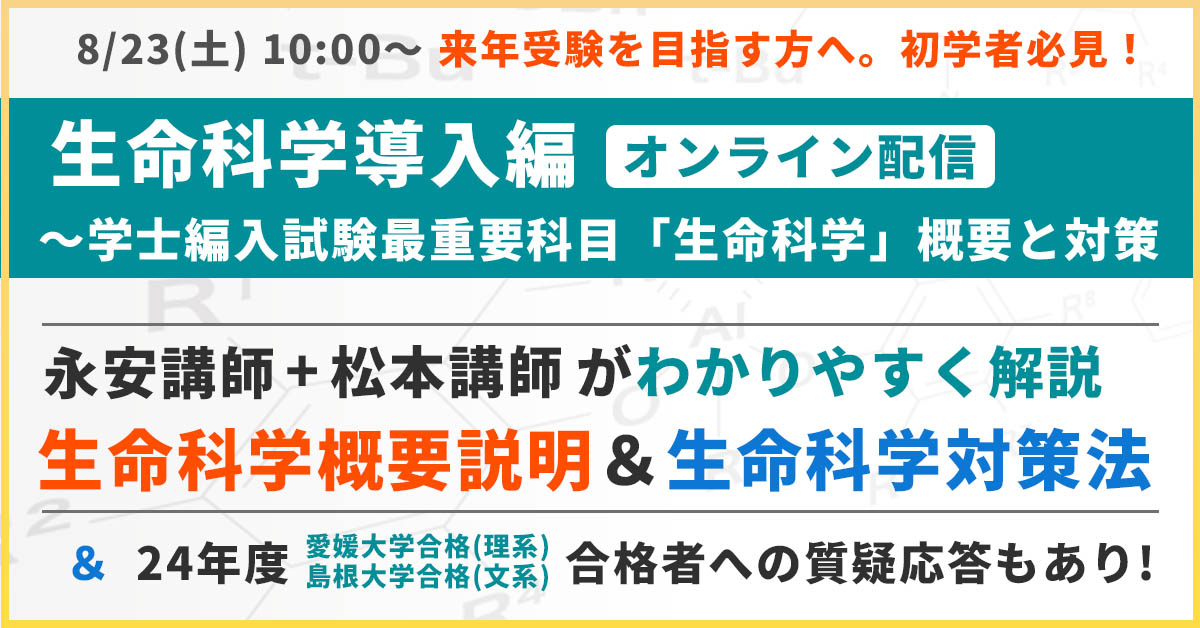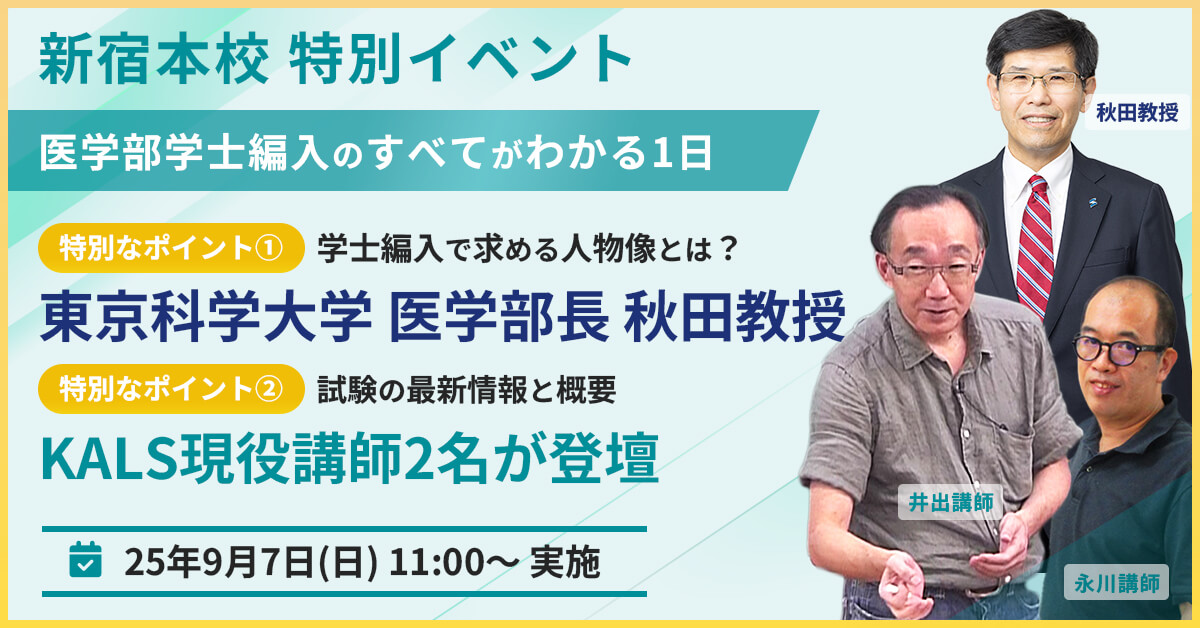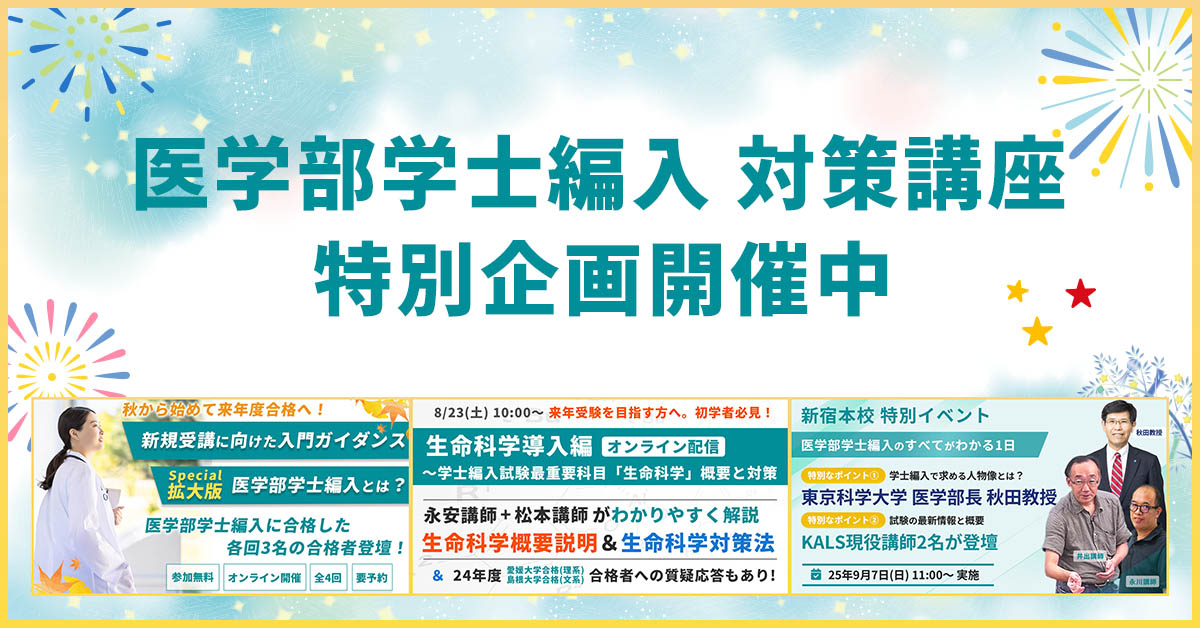21年 山口大学 医学部学士編入試験合格者 合格体験記
20代後半女性。国立大学医学部保健学科卒、看護師。
臨床での経験から、女性のがん治療と妊娠の両立に悩む患者さんを多く見、そのような患者さんの力になりたいと思い、医師になることを決意。19年終わり頃から学習を開始。21年3月に仕事を退職し、受験勉強に専念。21年11月に山口大学に合格。
プロフィール
医学部編入に至るまでの経歴
もともと女性の健康について興味があり、医学部保健学科の看護学専攻に進学しました。大学時代に海外での語学研修や学生団体での活動を経験し、卒業後は看護師として勤務していました。20年は新型コロナウイルスの影響で仕事が激務になり、十分な勉強時間が確保できず、受験のための県外の移動も難しくなったため、21年3月で退職しました。退職後は週に8時間ほど塾講のアルバイト(英語、数学、化学)をしながら勉強しました。
受験結果
| 20年 | 書類審査 | 筆記試験 | 面接試験 |
|---|---|---|---|
| 岡山大学 | 〇 | ※ | × |
| 福井大学 | ― | × | |
| 滋賀医科大学 | ― | × | |
| 大分大学 | 〇 | 〇 | × |
| 21年 | 書類審査 | 筆記試験 | 面接試験 |
|---|---|---|---|
| 琉球大学 | ― | 〇 | × |
| 香川大学 | ― | × | |
| 大分大学 | 〇 | × | |
| 岡山大学 | 〇 | ※ | × |
| 大学名 | 書類審査 | 筆記試験 | 面接試験 |
|---|---|---|---|
| 愛媛大学 | ― | 〇 | × |
| 滋賀医科大学 | ― | × | |
| 山口大学 | ― | 〇 | 〇 |
※岡山大学は筆記試験と面接試験が同日にあるため、面接試験にまとめた
医学部編入を目指したきっかけ
高校時代にも漠然と医学部を目指していましたが、センター試験で十分な点数を取ることができず、断念しました。看護師も非常にやりがいのある仕事であり、自分に向いていると感じてはいましたが、受け持ちの患者さんが亡くなったことがきっかけで、医師になることをもう一度考え始めました。ちょうどそのタイミングでKALSの説明会に参加し、19年の終わりに受験を決意しました。
KALSに入学した時期、KALSを選んだ理由、受講内容
20年1月から完成シリーズ(生命科学のみ)+実戦シリーズセット(通信)を受講しました。通信を選択した理由は当初は仕事と両立して勉強しようと考えていたため、不規則な勤務に対応しやすかったからです。21年はオプションでハイレベル確率・統計の講座と、志望理由の対策講座を受講しました。
志望校を選んだ時期、理由
高校時代に数学3C、生物1・2、化学1・2を履修済みでした。英語はセンター試験で95%以上を維持できるレベルでした。生物を中心に大学でも履修していたものもありましたが、専門以外はすっかり忘れてしまっていました。そのため、受験校としては生命科学と英語で受験できる大学に加え、高校レベルから大学初歩レベルの化学を出題する学校、文系でも合格実績のある大学を視野に受験しました。2年目は高校レベルの物理を学習したため、そのレベルで対応できる大学を追加して受験しました。(香川大学は関西から近かったので受験しましたが、撃沈しました。)
勉強方法
入試までに勉強した科目
1年目は生命科学を中心に学習し、滋賀・大分の受験前に高校レベルの化学を思い出す作業をしました。2年目は物理の学習にも力を入れました。
得意科目、不得意科目
得意科目:英語 (とはいえ、受験で自分よりももっとできる方に多くお会いしたため、途中で自信を失いました。)
不得意科目:物理 (高校時代から強い苦手意識がありましたが、最後まで好きにも得意にもなれませんでした。)
各科目の勉強法(具体的に)
生命科学
(1年目)
一番時間を割いて学習しました。完成シリーズは予習→講義(動画視聴)→復習のサイクルで学習し、知識があいまいな部分は高校生物や、看護学生時代のテキスト等を見て補足しました。実践シリーズは時間の関係上、予習はせず復習に力を入れるようにしました。完成・実戦シリーズ共に、ワークブックまでは手が回りませんでしたが、完成シリーズは予備問題も含め、なんとか3周しました。要項集についてはコロナウイルス前の1~3月は授業に合わせて読んでいましたが、4月以降はたまに気になる単元に目を通す程度で、完成シリーズレベルの問題を解けるようになることを優先しました。
(2年目)
仕事を辞めて時間ができたため、完成シリーズをさらに2~4周しました。実戦シリーズも1年目にできなかった予備問題や復習問題等も含めて取り組み、3周程度行いました。また、完成シリーズのワークブックも取り組みました。実戦シリーズのワークブックは頻出分野のみ何とか取り組みましたが、十分な演習までは行えませんでした。岡山大学の受験に合わせて、要項集も読み進め、記述練習としても活用しました。
英語
(1年目)
ほとんど学習に時間を割くことができませんでした。最低限として、ターゲット1900のアプリを使用して単語だけ隙間時間に学習しました。
(2年目)
英語以上に優先すべき科目が多かったこともあり、2年目も十分には学習していませんが、TOEIC、TOEFL受験前はしっかり取り組みました。1年目を経て、単語力が足りないと分析し、ターゲット1900を完全に覚えた後は、Appendixに収録されている英文を読み、足りない単語をその都度覚えていきました。単語の覚え方としては、暗記用アプリ等も試しましたが、私には100均の単語カードが一番良かったです。また、英文を読んで内容はわかっても、日本語訳がうまくできない問題も入試では多くあったため、英文を読むときは日本語訳を横に置いて、1文ずつ訳していくという練習もしました。ただし、これは和訳の練習としては良いですが、英文を読むという意味では時間がかかって、非効率的なので、学習のバランスは考えた方が良いように思います。
科学
新たなことは学習せず、これまでに習ったことを思い出すことを目標に学習しました。有機・無機化学に関してはスタディーサプリで動画を見ましたが、きれいにまとまっていて、高校時代に学習していたよりも理解できたように感じました。
物理
仕事を辞めると決めてからすぐに取り掛かりました。まずはスタディーサプリを一通り見て、全体像を理解した後、「橋本流はじめから~」シリーズを全シリーズ読みました。その後、問題演習を行いました。最後まで得意にはなれませんでしたが、高校物理を一通り勉強したおかげで、物理を出題する大学も受験することができました。
その他
統計は大学時代に少し学習しましたが、記憶の彼方だったため、2年目はハイレベル確率・統計を受講し、学習しました。受験が終わってから気づきましたが、現在は高校数学Bに統計が含まれているため、青チャートなどで基礎を完成させておいた方がとっつきやすいかもしれません。また、小論文については第1・2講の志望理由の講座に力を入れ、何度も書き直しましたが、それ以外については面接対策を兼ねてレジュメを見ながら、構想を書いたのみで、実際には書きませんでした。山口大学では数学(おおむね高校レベル)が出るとのことでしたが、アルバイト先で数学をメインで教えていたこともあり、積分の計算や、現在高校の教育課程から外れている行列のみ復習しました。しかし、実際は偏微分など高校数学で対応できない問題も出たため、どの程度正解できたかはわかりません。
実力テスト、公開模試の成績
正確な成績は不明ですが、生命科学に関しては常に偏差値50台でした。
英語については偏差値60台前後をうろうろしていたと記憶しています。
成績自体はあまり良くなかったですが、点数や偏差値よりも復習に力を入れ、解説を読んで理解できない問題については解説動画も参照しました。
おすすめ図書
「休み時間の免疫学」(講談社)
過去の合格者の体験談でよくおすすめされていたので、購入しました。コンパクトにまとまっていたため、隙間時間に読みやすく、学習の導入としてはおすすめです。
「細胞の中の分子生物学」(blue backs:講談社)
1年目の受験を終えて、2年目に入る前に読みましたが、この本によってあいまいだった部分が少しつながったと感じました。京大の先生が文系学生にもわかるようにという講義がもとになっているので、導入としてもわかりやすいかと思います。(とはいえ、個人的には生命科学の知識が全くない状態で読むと、苦痛に感じるのではないかと思います。)
「恋する医療統計学」(南江堂)
知り合いから譲ってもらった本ですが、統計の学習の導入としては非常に読みやすく、苦手意識が薄れる本でした。全体的に会話調で書かれていますが、特に、定義や解釈の仕方はわかりやすかったです。その他看護時代のテキストなどで重宝したものもありましたが、新たにそろえるものではないと思うので、ここには記載しません。
これから医学部編入を目指す方へエール
看護師からの受験は、看護師が嫌だから医師を目指すんでしょう、といった意地悪な質問も何度かされるなど、面接では苦労しました。医療系出身の方は、職業としての距離が医師と近いため、自分の職業を悪く言わず、かつ、その強みを生かして、さらに医師としてどのように活躍できるかを具体的に説明できる必要があると感じました。私が合格した大学では、面接で、私の看護師としての経験を評価していただけるような発言が面接官の先生からあり、今振り返れば、何度もの面接を経て、その部分をブラッシュアップできたのではないかと考えています。
また医療系の方は学生の頃から将来の職業が決まっているため、どうしてもそれが軸になりがちですが、自分の元の職業にとらわれず、自分にしかできないことや経験について話しても良いと思います。
そして、当たり前ですが、筆記試験でよい点数を取ることが必要です。これは私の持論ですが、一般的に学歴が高い人が受かるのは、大学受験時にその大学に入れるだけの努力をした、というポテンシャルが評価されているからだと思います。その方々と勝負するには今の試験の実力で上回るしかないと思います。
私自身、周囲がどんどん合格を手にする中、特に面接試験で落ち続けることは本当につらかったですが、自分の強みをアピールし、最後まであきらめずに頑張り続けたことが合格につながったと考えています。
私の体験記が少しでも似た境遇の方のモチベーション維持、向上につながれば幸いです。
最後になりましたが、KALSの先生方、スタッフの方々、推薦書を書いてくださった先生、いつも応援してくださった家族や友人、元職場の同僚には本当に感謝しています。ありがとうございました。