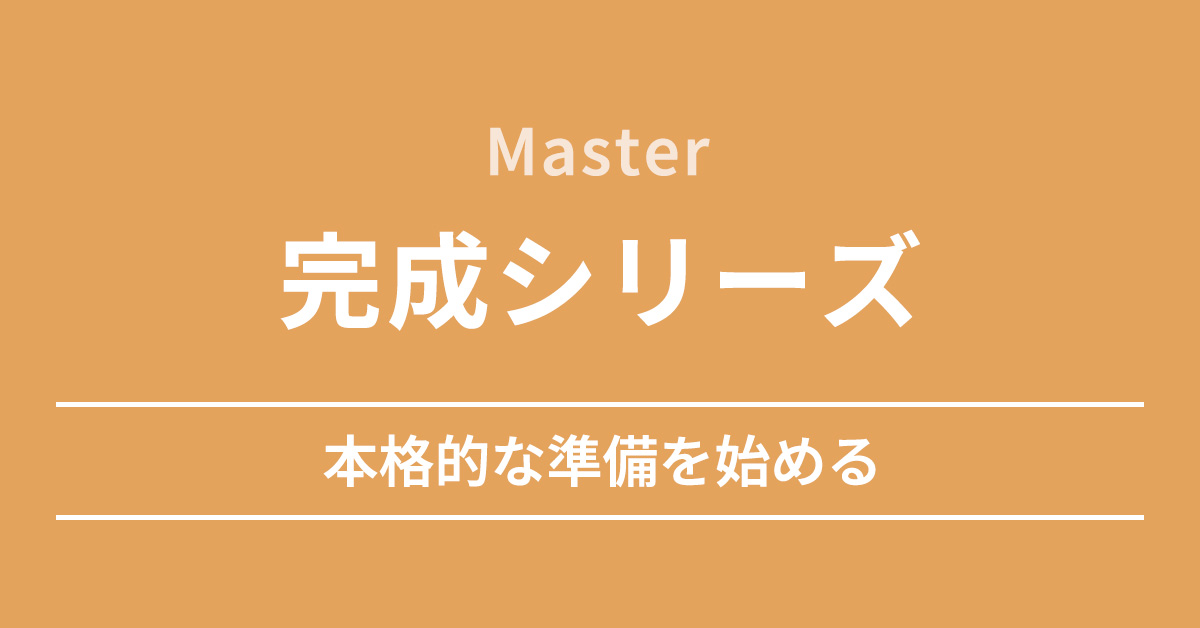24年 浜松医科大学 医学部学士編入試験合格者 合格体験記
30代、女性。国立大学の機械系修士、社会人を9年ほど経験。受験時は仕事をつづけながら勉強。
プロフィール
医学部を目指した経緯
高校生の時、医学部への進学を検討したこともありましたが、当時は別の分野を学びたいという気持ちが強く、受験には至りませんでした。結果として選んだ大学での学生生活は非常に充実したもので、今でも物理学が大好きです。この時の経験が、学ぶことへの意欲をさらに高めてくれました。学ぶこと自体が非常に好きで、将来、別の分野でもう一度大学で学びたいと常々考えておりました。 そのような中、30代になって間もなく手術を受けることになり、人体の構造や機能に強い興味を持つようになりました。この経験が、医学を学びたいという思いを決定づけるものとなり、今回の医学部編入を決意いたしました。
受験先と受験結果
| 受験先 | 1次 | 2次 |
|---|---|---|
| 浜松医科大学 | 合格 | 合格 |
2025年度の試験に向けて本格的に準備を進めていましたが、試験本番での過度な緊張を避けるため、まずは試験の雰囲気に慣れることを目的に、2024年度の試験も受験いたしました。そのため、2024年度は浜松医科大学1校のみの受験となりましたが、幸いにも合格をいただくことができました。この結果を受け、2024年度で受験を終了することにいたしました。 2025年度は、浜松医科大学に加え、大阪大学、筑波大学、北海道大学、滋賀医科大学の受験を検討していました。
受験校選び
自身の得意科目である物理の知識を最大限に活かし、他の受験生よりも優位に立つことを目指し、物理が出題範囲に含まれる大学を中心に志望校を選定しておりました。
各科目の勉強方法
KALSの受講コース
受講科目の選択など、学習計画に関わる意思決定の負担を最小限に抑え、勉強そのものに集中できる環境を整えたいと考え、KALSの総合コースを受講しました。総合コースには担任制度があり、専任のスタッフの方が個別にサポートしてくださるため、疑問点や不安な点をすぐに相談でき、非常に心強かったです。
生命科学
KALSの生命科学では、基礎シリーズ、完成シリーズ、実戦シリーズを通して、徹底的に知識の定着と応用力の養成を図りました。
基礎シリーズは、以下の内容を繰り返していました。
e-learningを受ける→ノートの内容をまとめる→新宿校で講義を受ける→ノートのまとめ内容を追加する→まとめを覚える→確認テストを受ける→ワークブックを解く
完成シリーズ、実戦シリーズは、講義内容が問題演習になるので、上記の流れの前に予習として問題を解く工程を入れていました。 ワークブックは必ず全部解き、3周くらい繰り返すのがおすすめです。
また、わからないことがあるときは、講義の前後に井出先生に質問していました。毎回とても分かりやすく教えてくださいました。
英語
大阪大学の出願には、TOEICのスコア提出が必要だったため、3回受験しました。TOEICは会場の当たりはずれもあるので、何度か受験できるように余裕をもって日程を組んでおくと安心だと思います。 2024年4月ごろから対策を初めて、秋ごろには目標スコアを達成していました。 また、大学独自試験を課す大学の対策のために、KALSの英語の講義を受講していました。英語はなるべく毎日触れたほうが良いだろうと考え、KALSの教材以外にも、軽めの問題集などを解いていました。
物理
もともとの専門分野が物理系なので、基礎シリーズの物理の講義は受けませんでした。物理のエッセンスをさっと1周解いて、忘れているところを思い出すくらいでした。 夏ごろから物理化学シリーズが始まるので、物理化学シリーズはきちんと受講しました。
化学
化学は得意科目ではなかったため、まずは高校範囲の復習から着手しました。その後、KALSの物理化学シリーズを受講しましたが、苦手意識を完全に払拭するには至らず、試行錯誤しながら受験当日まで学習を続けました。
数学
筑波大学の試験科目には数学が含まれていたため、対策を検討しました。KALSのチューターの方から、青チャートレベルの問題を習得すれば十分であるとのアドバイスをいただき、参考書を購入しました。しかし、他の科目の学習を優先した結果、本格的に取り組む前に受験を終えることとなりました。
小論文
文章を書くことに対してとても苦手意識があり、浜松医科大学の2次試験の前に3つほど講義を受講して添削をしていただきました。講義内容も分かりやすく、また周辺知識のインプットもあるので非常に助けになりました。
その他
志望理由書
文章を書くことへの苦手意識から、志望理由書の作成にはなかなか着手できずにいました。そこで、まずはKALSのチューターの方に相談し、志望理由書に盛り込むべき要素や構成について、具体的なアドバイスをいただきました。
いただいたアドバイスを基に、自身の経験や思いをどのように表現すれば、より効果的に伝えられるかを熟考し、文章を練り上げていきました。
KALS総合コースには添削講座も含まれていましたが、浜松医科大学の出願締め切りが比較的早かったため、今回はこの講座を利用せずに出願しました。2025年度の出願に向けては、この添削講座を活用し、さらに完成度の高い志望理由書を作成したいと考えておりました。
推薦書
推薦書は、大学院時代の指導教員に依頼することにしました。まず、先生に連絡を取り、直接大学まで伺って推薦書作成のお願いをいたしました。先生は快く引き受けてくださり、大変心強く感じました。快く協力してくださった先生に良い報告をしたい、と気合が入りました。
面接
KALSで公開されている過去の面接試験に関する資料を参考に、想定される質問とその回答をまとめた想定問答集を作成し、面接対策を行いました。資料には、面接は和やかな雰囲気であったと記されていることが多かったのですが、私が実際に経験した面接は、少し緊張感のある雰囲気でした。
学習相談
復習テストや中間テストなどの節目に、井出先生による学習相談の機会が設けられていました。私は毎回この学習相談に申し込み、積極的に活用させていただきました。井出先生は、いつも穏やかで親身になって相談に乗ってくださり、学習の進捗状況や理解度に合わせて、的確なアドバイスや励ましの言葉をかけてくださいました。先生との対話を通して、学習意欲をさらに高めることができ、大変感謝しております。
台風
浜松医科大学の一次試験前日、台風10号の接近により、交通機関に大きな影響が出ました。新幹線や在来線は運転を見合わせ、高速道路も一部区間で通行止めとなるなど、移動手段が著しく制限される状況でした。私は、2024年度の試験はあくまで場慣れを目的としていたこともあり、安全を最優先に考え、受験を断念することも視野に入れていました。 しかし、夫は「このような状況だからこそ、受験者数が減り、合格の可能性が高まるはずだ。ぜひ受験するべきだ。私が車で送る。」と強く勧めてくれました。夫の言葉に背中を押され、急遽、自宅のある東京から試験会場のある浜松まで、車で向かうことになりました。 結果として、この年の試験で合格をいただくことができ、予定よりも1年早く受験を終えることができました。困難な状況の中、私を支え、送り出してくれた夫には、感謝してもしきれません。
最後に
私が医学部学士編入を検討し始めた際、既に編入試験を経験した複数の友人から、「KALSを選べば間違いない」と強く勧められ、KALSへの入塾を決意しました。そして今、自身の合格体験を振り返ってみても、友人たちと同じように「KALSを選んで本当に良かった」と心から確信しています。 KALSの講師陣、事務スタッフの方々、そしてチューターの方々、全ての方が、受験生一人ひとりの目標達成を全力でサポートしてくださいます。ぜひ、皆さんもKALSを最大限に活用し、医学部学士編入という難関を見事突破されることを心より願っています。