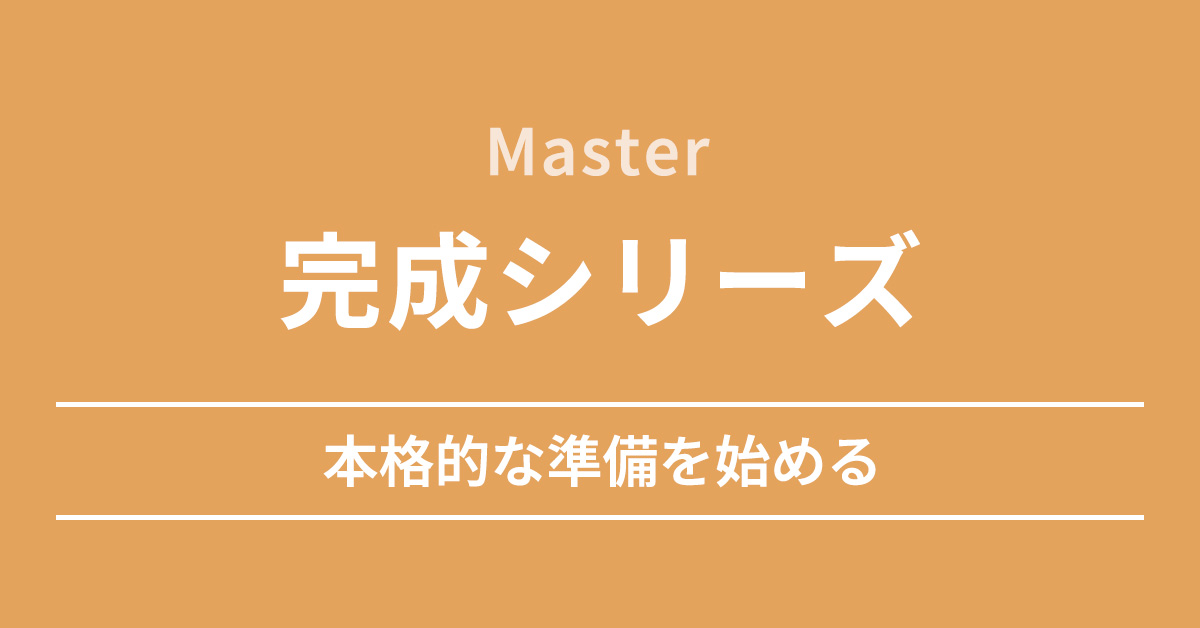24年 群馬大学・高知大学 医学部学士編入試験合格者 合格体験記
28歳、男性。国立大学生命科学系研究科修了後、製薬会社にて勤務。
業務で医師と関わる中で、自ら医師として患者さんに直接貢献したいと思うようになり、医学部受験を決意。2023年4月からKALSを受講し、本格的に受験勉強を開始。2024年3月に退職後、受験に専念し、2024年9月に高知大学、10月に群馬大学に合格。
プロフィール
医学部編入、学士編入に至るまでの経歴
地方国立大学工学部化学系学部卒業。都内国立大学大学院生命科学研究科修了後、製薬メーカーに勤務。2023年4月にKALSを受講開始。2024年9月に高知大学、10月に群馬大学に合格。
受験先と受験結果
| 大学名 | 受験結果 | 書類 | 一次(筆記) | 二次(面接・集団討論等) |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島大学 | × | |||
| 名古屋大学 | × | |||
| 香川大学 | × | |||
| 高知大学 | ○ | ○ | ||
| 群馬大学・高知大学 | × | |||
| 愛媛大学 | ○ | × | ||
| 島根大学 | ○ | 辞退 | ||
| 神戸大学 | × | |||
| 群馬大学 | ○ | ◎ |
×:不合格、○:合格、◎:進学先
進学先と進学先を選んだ理由
進学先:群馬大学
進学先を選んだ理由:群馬大学には大学院時代の研究テーマに関連する研究部門があり、入学後も同分野の研究をしていきたいと考えたため。また地元に近く、将来的には北関東の医療に貢献する医師になりたいと考えているため。
医学部編入、学士編入を志したきっかけ・時期
祖父をがんで亡くした経験から、幼い頃から医師への憧れを持っていました。しかし高校時代は、より多くの患者さんを救えるような新薬開発に関わる仕事に就きたいという思いがあり、化学系学科に進学しました。製薬会社の業務で医師と関わる中で、自ら医師として患者さんに貢献したいという思いや臨床研究を自ら主導していきたいという思いから、2023年1月に医学部受験を決意しました。
勉強方法
KALSに入学した時期・KALSを選んだ理由・受講内容
・2023年4月にKALSに入学しました。限られた時間の中でも効率的に勉強をすることができ、講師やチューターのカウンセリングや過去問閲覧等、合格に必要なエッセンスが揃っていることからKALSを選びました。
・基礎+完成+実戦コース(実戦のみ通学)、トップレベルテストゼミ、志望理由書対策講座を受講しました。
各科目の勉強法
生命科学
KALS受講開始前は、高校の教科書(生物基礎+生物)を繰り返し読んでいました。また、教科書と並行してYouTubeのtry it を視聴しました。KALS受講後は、KALSの教材のみを使用して勉強しました。基本的には、KALSのスケジュール通りに学習を進めました。井出先生の板書を書き写し、先生が話していることもメモして、理解できない部分は何度も見返して理解するようにしました。それでも分からない場合は、メールで質問しました。1回の講義で、3-4時間かかっていましたが、時間をかけて理解を深めていくことで、生命科学の土台を作ることができました。講義動画が終わった後は、必ず確認テストを受け、知識が定着しているかの確認をしました。基礎シリーズの1周目は通常の動画スピードで視聴し、2周目は1.5倍の速さで視聴して抜けている部分を穴埋めするイメージで学習しました。なるべく早く、筆記試験に対応できるくらいの学力をつけたいと思っていたので、講義動画と並行してワークブックを解いていました。選択問題は確実に解けるようにし、記述問題は分からなければ答えを見て、記述の仕方やどういう内容を書けば良いのかを理解し、解ける問題を増やしていきました。
英語
TOEICは、会社員時代の1年間に勉強して取得した810点を受験に使用しました。KALS受講開始後はTOEICの勉強は一切せず、医学英文法と医学英語演習をKALSのスケジュール通りに進めていました。
化学、物理
スタンダード化学、スタンダード物理を中心に学習を進めました。化学は得意科目であるため、重要問題集で演習をし、高校化学が一通り仕上がった後は大学範囲(使用した教科書は「ソロモンの有機化学」「アトキンス 物理化学」)に着手しました。苦手科目である物理については、KALSの教材としてセットになっている「宇宙一わかりやすい高校物理」を読み込んで、基礎的な内容から学習を進めました。
数学、統計
数学は大学時代に使用していた微分・積分学の教科書、統計はKALSの教材を使用して学習を進めました。
小論文
KALSの小論文演習をスケジュール通りに進めました。
1日の勉強時間、勉強時間を確保するための工夫や苦労など
・仕事と受験勉強を両立していた時期(約1年間):平日は1日約4時間。仕事が終わった後、自宅近くのコワーキングスペースで3時間ほど勉強し、帰宅後の就寝前に1時間勉強していました。休日は、1日約10時間。
・退職後、受験勉強に専念していた時期(約半年間):平日休日問わず、1日約10時間。勉強していた時間帯は、9時-12時、14時-19時、21時-23時で、それ以外は昼寝・食事・入浴をしていました。
・勉強時間を確保するためには、1日のルーティンを作ることが重要だと思います。また、自分が集中しやすい環境を作ることも重要です。スマホは勉強に入る時にはわざと自分から遠いところに置いていました。
家族の反応など
・家族全員が快く応援してくれて、支えてくれました。
スランプ克服法
・どれだけ勉強しても伸びない場合:勉強方法に何か問題がある可能性が高いので、チューターや講師の先生方に相談して、客観的な意見をもらうのが良いと思います。
・やる気が出ない場合:チューターに相談しても良いのですが、結局最後は自分次第です。私自身も、やる気が出ないなと思う時が何回もありました。その時には、「情熱は足りているか?医師になりたいという自分の情熱はその程度のものなのか?」と自分に言い聞かせていました。人間誰しも、やる気がなくなる時があると思います。その時に自分に負けてしまうのか、それとも自分を奮い立たせて少しでも勉強を続けるのか、このどちらを選択するかが合否に繋がっていると信じて、モチベーションを維持していました。
その他、受験勉強を経験した感想など
・通学されている方は、ぜひクラスメイトに声をかけてみるといいと思います。私は実戦シリーズから通学に切り替えて授業を受けていましたが、休み時間に「友達になってください。」と自分から声を掛けました。情報交換・切磋琢磨できてモチベーションも維持できると思います。
・受験を通じて、合格のために重要だなと感じたことは、「自分がしている勉強や過ごしている時間が、合格に繋がるための時間になっているかどうかを常に自分自身に問いかけること」です。私が毎日実践していたことは、体調を維持するためにバランス良く食事を摂る、医療の最新情報を吸収するために新聞や医療ニュースを読む、勉強の質を高めるために昼寝をする、質の良い睡眠を取るために入浴後にストレッチする、どのような医師を目指すか・どのように医療に貢献していきたいかの自己分析を徹底的にする、などです。ここまで徹底している受験生は他にいないだろうと思えるくらいやっていれば、いつの間にか自分でも信じられないくらいレベルアップしているはずです。
・受験は他の受験生との勝負と思いがちですが、私はどちらかというと自分と向き合うことの方が大切だと感じました。自分と向き合って今の自分のレベルを認識し、合格という到達点までに足りていないものを一つ一つ埋めていくことが重要だと思います。
その他
医学部へ編入するにあたっての抱負
・将来は腫瘍内科医として、臓器横断的に、数多くのがん患者さんに最適ながん薬物療法を提供できる医師、そして臨床研究を積極的に行ってより良い治療薬や治療方法を開発していく医師になりたいと思っています。
これから医学部編入を目指す方へ
・私は受験勉強を始めた当初は、合格体験記の方々のように自分も合格できるのかな、という不安で押しつぶされそうでした。でも、決して不可能なことはないと思います。「医師になるんだ!」という情熱を持って、合格に必要な事を積み重ねていけばきっと良い結果が待っていると思います。
・最後に、KALSの先生方、校舎スタッフの方々、チューターの方々、皆様一人一人にご支援をいただいたおかげで合格することができました。本当にありがとうございました。
・この合格体験記が、これから受験に臨む皆様に少しでもお役立てできれば幸いです。受験生の皆様一人一人の想いが実を結ぶことを心から願っております。