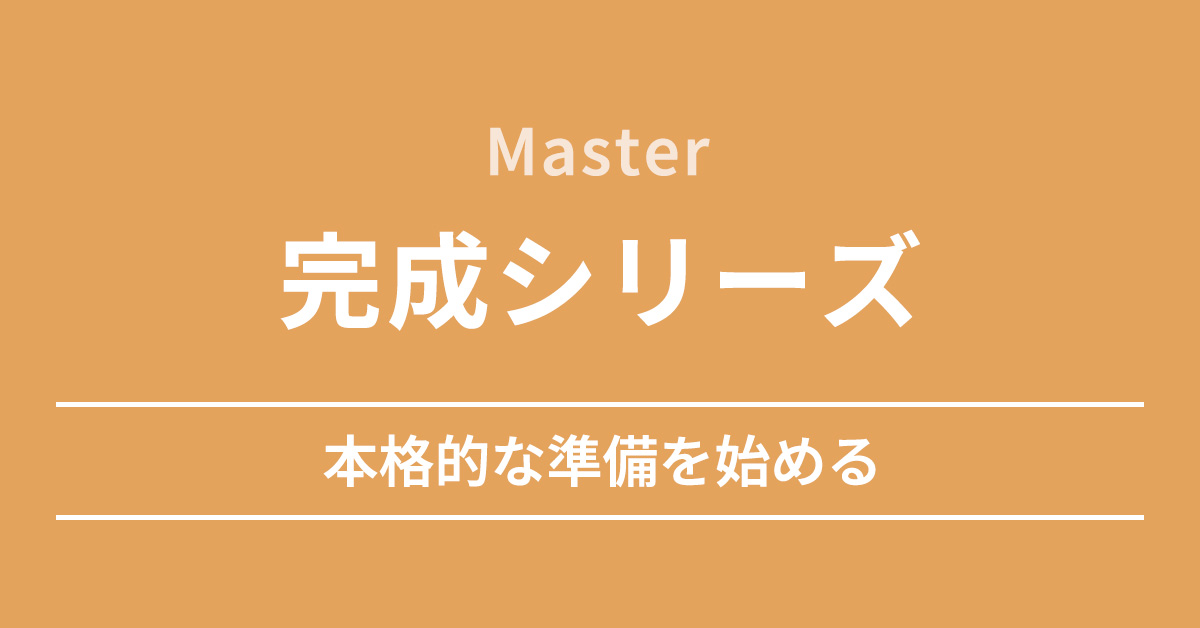24年 旭川医科大学 医学部学士編入試験合格者 合格体験記
29歳、女性。私大文系学部卒業後、外資コンサルティングファーム勤務。
出産、移住の経験から医師偏在の課題を実感し、医学部受験を決意。2023年夏頃から受験勉強を開始し、仕事と育児と両立しながら2024年12月旭川医科大学に合格。
プロフィール
受験校と結果
家庭の都合から、自宅から通える範囲にある旭川医科大学のみ受験(進学先)。
医学部編入、学士編入を志したきっかけ・時期
第一子出産時に出血が止まらなくなる場面があり、医療従事者の方々に迅速に対応いただき命を救っていただきました。その時の感謝と尊敬の気持ちが医療職への憧れを抱くきっかけとなりました。加えて、移住を機に北海道内における医師偏在に対する課題意識を深め、医師として貢献する決意をしました。趣味の範囲ではありますが、もともと医学に興味があったことも後押しとなりました。仕事と育児をしながらの受験になるため、科目数が少なく、これまでのキャリアを活かせる学士編入を志し、比較的時間がとれた第二子の育児休暇中に学習を開始しました。
勉強方法
KALSに入学した時期・KALSを選んだ理由・受講内容
2023年夏頃に入学しました。限られた時間で必要知識をインプットし、合格水準までアウトプット力を高めるためには、医学部学士編入試験で長年の実績があるKALSへの入学が最も効率的だと考えました。KALSでは主に、生命科学(基礎・完成・実戦・トップレベル)、医学英語演習、統計を受講し、直前期には旭川医科大学の過去問演習講座と2次試験に向けた面接対策講座も受けました。(内容が面白いので、トップレベル生命科学まで受講されることをお勧めします。)
入試までに勉強した科目
対策が必要な科目は、旭川医科大学の出題科目である生命科学、英語(、統計)でした。もともと英語が得意(TOEIC 900点後半)であり、かつ生命科学の配点が最も高かったことから、勉強時間のほとんどを生命科学に全振りする作戦で学習を進めました。英語はKALSのテストや医学英語演習で定期的に客観的な得点力や立ち位置を確認するくらいでした。統計は出題されない年もあったので、統計の講座の中でも主要な講のみ理解できるようにしていました。
各科目の勉強方法
生命科学:KALSのコンテンツを最大限活用する作戦で、受講→確認テスト→ワークブック→記述テスト(→要項集)のサイクルを遵守し、通学生の標準スケジュールから遅れないように計画していました。自分で説明できない箇所を徹底的になくすことを意識し(基礎部分は特に)、出来るまで該当箇所の再受講や演習を繰り返しました(3~10サイクルほど)。一通り習得した後は、テキスト・ワークブック・要項集の問題演習を繰り返して苦手分野の特定・解消に努めました。また、子供の送り迎えや習い事の待ち時間等の隙間時間も活用したく、講座の音声データを聞いたりテストエンジンを実施したりしていました。受験までの時間は限られているため、幅広く色々するのではなくKALSで提供される内容をしっかり自分のものにしようという考えでした。
志望動機書作成:勉強ではないですが時間をかけて作成する必要があり(想定以上に時間を要するものだと思います)、旭川医科大学に通っているチューターの方にアドバイスを貰いながら最終化させていきました。志望動機書を読む教授群は論理の飛躍や矛盾に即座に気付くはずなので、そういった点が無いかを特に気にするようにしていました。
KALS 実力テスト、公開模試の目標設定、成績について
(数値=偏差値)
| テスト名 | 生命科学 | 英語 |
|---|---|---|
| 基礎シリーズ復習テスト③ | 57.5 | - |
| 基礎力判定テスト | 63.6 | 64.3 |
| 単語テスト① | - | 64.3 |
| 単語テスト② | - | 62.9 |
| 単語テスト③ | - | 60.4 |
| 実力テスト② | 65.5 | 62.5 |
| 第1回公開模試 | 66.3 | 62.7 |
| 第2回公開模試 | 64.6 | - |
| 第1回テストゼミ | 69.9 | - |
| 第2回テストゼミ | 50.3 | - |
| 第3回テストゼミ | 73.1 | - |
| 第4回テストゼミ | 65.8 | - |
| 第5回テストゼミ | 61.4 | - |
記載時点で偏差値が分かるもののみ記載しています(テストは全て受けました)。各テストでは偏差値60を目標にしていました。受験生の中で常に上位にいれば合格可能性が高い=自分の受験対策の方向性に大きな誤りはないと言える、という考えでした。傾向として、生命科学は偏差値60付近をキープできているものの問題によっては下回っていたため、全体的な底上げが終わってからは特に苦手な分野の復習に力を入れました。英語は能動的な学習はほぼしていないものの安定的に60以上はとれていたため、勉強時間をあまりとらないことは受験をする上で特に問題ではないと判断していました。
1日の勉強時間、勉強時間を確保するための工夫や苦労など
受験勉強を開始してからの前半約6ヵ月は育児休暇中であったため、子供の起床前、昼寝中、就寝後等の時間を活用して5~6時間、後半約6ヵ月は復職していたため、平日3~4時間、休日4~5時間を勉強に充てていました(特に計測していなかったので大体の目安として参考にしてください)。受験勉強はあるものの、子供の成長や家族のイベントも勿論大事なので、実家への帰省や家族旅行、地域イベントへの参加もしていました。医学生/医師になっても、バイト/仕事と育児とを両立させながらやるべきタスクをこなして結果を出していく必要があり、その点においては受験勉強でも同じことが言えるため、全てを後回しにする必要はないと考えていました。勉強時間よりも決めたスケジュールに対する進捗状況や定期的な試験の結果、苦手分野の有無と解消具合を気にしていました。夜間授乳もあり体力的に疲労を感じることも多く、睡眠を優先させる日もありました。早めに就寝した日は夜中に子供に起こされてからそのまま早朝まで勉強する等、1日の中でスケジュールは固定せずに出来るときに柔軟に学習を進めるようにしていました。
スランプの有無とスランプ克服法
スランプとは違うかもしれませんが、復職後に思うように時間がとれずにもやもやとした気持ちを抱える時期がありました。とはいえ思い悩んでも仕方ないので、自分が置かれている状況の中で変えられないこと(仕事と育児に一定時間を割かねばならない)に対してあれこれ考えるのは止めて、変えられることは何か?を前向きに具体的に検討していました。実際に変えた点としては、働き方(稼働時間を減らせる時は躊躇わずに減らす)と学習タスクの優先度(例えばですが、10割理解を目指す→9割でいったん良しとして苦手分野に進む)、隙間時間の使い方、等がありました。また、そういった試行錯誤の過程を経ることで、様々ある状況下でも出来る範囲で努力している自分に対する信頼度のようなものが向上していきました。
その他、受験勉強を経験した感想など
私にとっての受験勉強は主に生命科学の学習でしたが、医学に直結する内容で興味深く、総じて楽しかったです。オンライン受講ではありましたが、井出先生に教わることが出来て本当に良かったです。
その他
これから医学部編入を目指す方へエール
試験会場で発揮する数時間のパフォーマンスが受験勉強の集大成になります。試験本番は緊張しますが、会場ではとにかく落ち着いて最大限の力を出すことが重要です。そのためには、会場で問題用紙に向かう際に解答者としての自分を信頼できると言えるようになるだけの努力を日々実直に積み重ねていくことが大事なのではと思います。壁を感じる時は辛いかもしれませんが、その先には知識が広がる喜びが待っています。ぜひ勉強を楽しみながら頑張ってください!